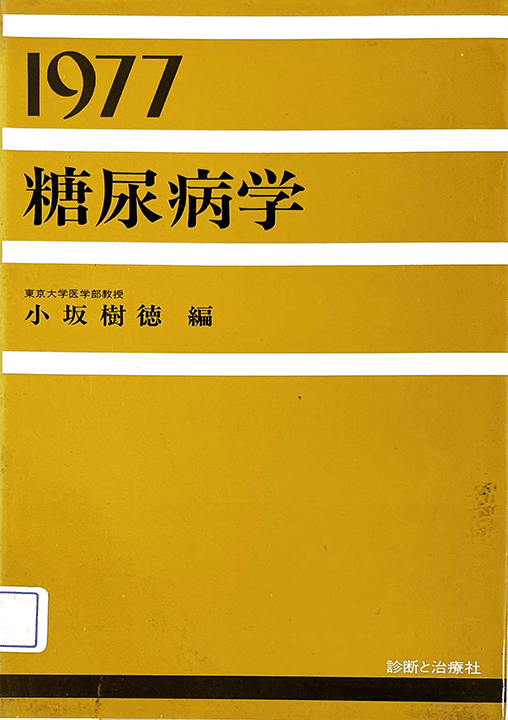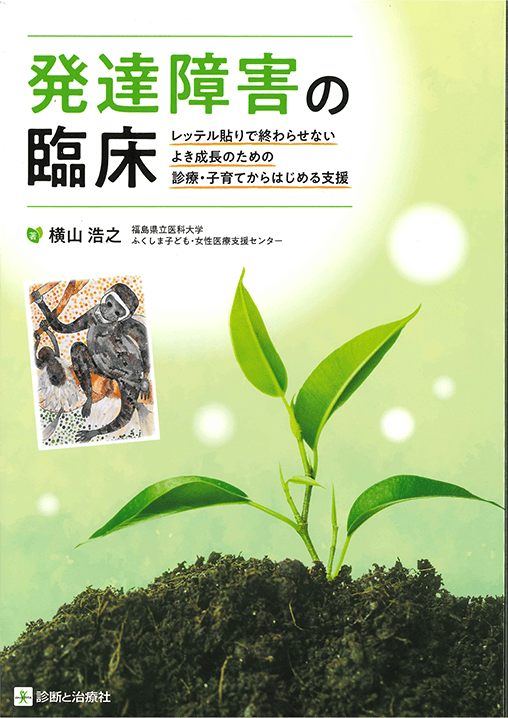診断と治療社110年のあゆみ
1914年~1939年
社会・医学界のおもな出来事
110年のあゆみ・各年代の代表的刊行物の紹介(雑誌/書籍)
1914年
大正3年
社会・医学界のおもな出来事
- 第一次世界大戦勃発
- 第4回日本医学会総会開催
- 北里柴三郎、北里研究所を創立
- 創業者・藤實人華、近世医学社(現・診断と治療社)創業
- 日本初の臨床総合誌「近世医学(現・診断と治療)」創刊。以降、現在まで刊行中
1919年
大正8年
社会・医学界のおもな出来事
- スペイン風邪(インフルエンザ)の世界的大流行
1922年
大正11年
社会・医学界のおもな出来事
- フレデリック・バンティングとチャールズ・ベストが膵臓インスリンを発見
1923年
大正12年
社会・医学界のおもな出来事
- 関東大震災発生
- 関東大震災で東京・牛込の本社社屋の倒壊は免れたものの、工場や倉庫は全焼、すでに印刷済みであった発行前の雑誌がすべて焼失するなど、甚大な被害を受けたが刊行継続
1926年
大正15年
- 社名を「近世医学社」から「診断と治療社」に改名し、雑誌「近世医学」を第13巻より「診断と治療」に改称
1928年
昭和3年
社会・医学界のおもな出来事
- アレクサンダー・フレミングがペニシリンを発見
1929年
昭和4年
- 「起り易き診療上の過誤と其注意(診断と治療臨時増刊シリーズ)」(茂木蔵之助・山田章太郎 編纂)発刊
1930年
昭和5年
社会・医学界のおもな出来事
- 宮城 順が胃の内視鏡を日本で初めて紹介する
1931年
昭和6年
- 「児科診療叢書」(小山武夫・鎮目専之助・小田正暁 編纂)発刊
1933年
昭和8年
- 日本初の産婦人科誌「産科と婦人科」創刊。以降、現在まで刊行中
1935年
昭和10年
- 丸の内(三菱21号館)に事務所移転
- 日本初の小児科誌「児科診療(現・小児科診療)」創刊。以降、現在まで刊行中
1940年~1959年
社会・医学界のおもな出来事
110年のあゆみ・各年代の代表的刊行物の紹介(雑誌/書籍)
1941年
昭和16年
社会・医学界のおもな出来事
- 日本軍がハワイ真珠湾攻撃、太平洋戦争開戦
1943年
昭和18年
社会・医学界のおもな出来事
- 薬事法公布。医師の調剤権が確立される
- 「胃鏡診断法」(桐原眞一 著)発刊
1945年
昭和20年
社会・医学界のおもな出来事
- 太平洋戦争終結
- 広島・長崎への原爆投下による被爆者治療のため、放射線医学が日本で進展
- 太平洋戦争の戦局悪化による紙の配給制限などにより3誌すべて一時休刊※画像は戦時中の「診断と治療」(第32巻第5号)、国立国会図書館所蔵
- 終戦後、本社のあった丸ノ内のビル(三菱21号館)がGHQに接収、社長自宅を事務所として事業継続
- 雑誌「診断と治療」休刊後、数か月で復刊
1946年
昭和21年
社会・医学界のおもな出来事
- 医療制度審議会、医学教育審議会発足
- 第1回医師国家試験を実施(受験者267人)
- 雑誌「産科と婦人科」復刊
- 「医学上より見たる産児制限と其方法」(久慈直太郎 著)発刊
1947年
昭和22年
社会・医学界のおもな出来事
- 医師国家試験を全国的に実施
1948年
昭和23年
社会・医学界のおもな出来事
- 世界保健機関(WHO)発足
- 保健婦助産婦看護婦法を制定
- 厚生省、「母子手帳」を配布
- 予防接種法施行。インフルエンザワクチンなどの接種がはじまる
- 雑誌「児科診療」復刊
1949年
昭和24年
社会・医学界のおもな出来事
- 厚生省、ペニシリン使用の決定
- 「醫師國家試驗豫想問題と答案 / 附・醫師國家試驗問題集」(原 義雄・今井 守・木村和郎・宮尾眞智子 共編)発刊。以降、1979年版まで刊行※右の画像は「1979年版医師国家試験問題集」
1950年
昭和25年
社会・医学界のおもな出来事
- 宇治達郎らが胃カメラを開発
- 診断と治療社、株式会社に改組
- 「医学シンポジウムシリーズ」発刊※左の画像は当時の目録より
1951年
昭和26年
社会・医学界のおもな出来事
- サンフランシスコ平和条約締結
- アメリカよりラジオアイソトープの輸入スタート、診断・治療などラジオアイソトープを用いた医学利用がはじまる
- 「新生児の取扱いと其知識」(久慈直太郎 著)発刊
1953年
昭和28年
社会・医学界のおもな出来事
- ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックがDNAの二重らせん構造を発見
- 雑誌「児科診療」を「小児科診療」に改称
- 本社社屋を丸の内の旧丸ビルに移転
1954年
昭和29年
社会・医学界のおもな出来事
- 国立東京第一病院(現・国立国際医療研究センター病院)で日本初の人間ドックを実施
1955年
昭和30年
社会・医学界のおもな出来事
- ジョナス・ソークが不活性ポリオワクチンを開発
- 6年制医学部発足(国公私立計35校認可)
- 診断と治療社各雑誌(「診断と治療」、「産科と婦人科」、「小児科診療」3誌合同)の編集委員、医学界有志の先生方による「藤實人華 喜寿祝賀会」が東京・品川プリンスホテルで開催
- 「沖中教授臨床講義集Ⅰ」(東京大学医学部沖中内科医局 編)発刊
1956年
昭和31年
- 「不眠症」「神経症」(ともに西丸四方著)発刊
1958年
昭和33年
- 「小児の治療保健指針(附・小児薬用量)」(高津忠夫・小林 登・平山宗弘 監修)発刊※画像は改訂第7版
- 「東大小児科治療指針」(高津忠夫 監修)発刊※画像は改訂第2版
1959年
昭和34年
- 「外科診療」創刊、以降1996年まで刊行 ※画像は国立国会図書館所蔵
1960年~1979年
社会・医学界のおもな出来事
110年のあゆみ・各年代の代表的刊行物の紹介(雑誌/書籍)
1961年
昭和36年
社会・医学界のおもな出来事
- 国民皆保険制度開始
1963年
昭和38年
- 藤實人華、逝去(享年84歳)
- 藤實廣由が二代目社長に就任
1964年
昭和39年
- 「小児薬用量」発刊※画像は改訂版、1995年「新 小児薬用量」発刊、以降2024年に改訂第10版刊行
1967年
昭和42年
社会・医学界のおもな出来事
- クリスチャン・バーナードが世界初の心臓移植手術を成功
- 人工透析の医療保険適用
- 「糖尿病学の進歩」(日本糖尿病学会 編)発刊、以降2012年まで刊行※画像は第12集
1968年
昭和43年
社会・医学界のおもな出来事
- 和田寿郎が日本初の心臓移植手術を実施
- 「脳の超音波診断」(田中憲二 著)発刊
1969年
昭和44年
- 日本小児神経学会学会誌「脳と発達」創刊、受託制作開始
1972年
昭和47年
社会・医学界のおもな出来事
- ゴッドフリー・ハウンズフィールドがCTスキャンを発明
- 「小児神経学の進歩」(日本小児神経学会学会 編/福山幸夫 責任編集)発刊、以降2019年まで刊行※画像は第6集
1973年
昭和48年
社会・医学界のおもな出来事
- 第2次田中角栄内閣、一県一医大構想(無医大県解消構想)を提唱。7年間で16校の国立医科大学(医学部)が計画的に新設
- ポール・ラウターバーがMRIの映像化に成功
- 医学部・歯学部を6年制に改正
1975年
昭和50年
- 「小児科当直医マニュアル」(神奈川県立こども医療センター小児内科 編)発刊。以降2023年に改訂第16版刊行※画像は改訂第2版国立国会図書館所蔵
1977年
昭和52年
- 「糖尿病学」(小坂樹徳 編)発刊、以降年刊形式で現在まで刊行中
1978年
昭和53年
- 「糖尿病の療養指導」(日本糖尿病学会 編)発刊。以降2012年まで刊行
- 「母子保健学」(国分義行・岩田正晴 著)発刊
1980年~1999年
社会・医学界のおもな出来事
110年のあゆみ・各年代の代表的刊行物の紹介(雑誌/書籍)
1980年
昭和55年
社会・医学界のおもな出来事
- ロバート・ギャロがHTLV-1ウイルスを発見
- 雑誌「老人科診療」創刊、以降1989年まで刊行※画像は国立国会図書館所蔵
1982年
昭和57年
社会・医学界のおもな出来事
- ウィリアム・デブリースが世界初の完全置換型人工心臓移植手術を施行
- 東芝がNMR-CTの国産第一号機を開発
- 「内科学(疾患編/症候編)」(小坂樹徳 監修)発刊※画像は当時の自社広告より
1983年
昭和58年
社会・医学界のおもな出来事
- ルック・モンタニエとロバート・ギャロがヒト免疫不全ウイルス(HIV)を発見
- 東北大学で日本初の体外受精妊娠に成功
- 「腎生検の病理 ー腎臓病アトラスー」(坂口 弘・北本 清 著)発刊
- 「カラーアトラスリアルタイムドプラ断層心エコー図法 : ドプラ断層の臨床」(尾本良三 編著)発刊
1984年
昭和59年
- 「産婦人科 漢方研究のあゆみ」第1号(竹内正七・坂元正一 監修)発刊、以降現在まで刊行中
1985年
昭和60年
社会・医学界のおもな出来事
- 厚生省が日本初のエイズ患者1号確認を発表。日本でHIV/エイズ対策が本格的にはじまる
- 「小児保健」(今村栄一・巷野悟郎 編著)発刊
1987年
昭和62年
社会・医学界のおもな出来事
- 利根川進が日本人初のノーベル医学生理学賞受賞
1989年
平成元年
社会・医学界のおもな出来事
- 消費税導入
-
「診断と治療」「産科と婦人科」「小児科診療」3誌の増刊号刊行スタート



-
「発達障害医学の進歩 第1集」(有馬正髙・熊谷公明 編)発刊、以降2016年まで刊行

1990年
平成2年
- 「視て学ぶ脳神経外科学」(郭 隆璨 編著)発刊
1993年
平成5年
- 「眼病変を読む : 全身疾患と眼 カラーアトラス」(田野保雄・澤 充・坪田一男 編)発刊
- 「l'oeil(ルイユ)(眼科学Year Book)1」(田野保雄・樋田哲夫・坪田一男 編著)発刊
1995年
平成7年
社会・医学界のおもな出来事
- 地下鉄サリン事件
- 阪神・淡路大震災発生
- 北大病院で日本初の遺伝子治療の臨床試験開始
- 「研修医ノート-医の技法」(永井良三 責任編集)発刊、以降研修医ノートシリーズの刊行
2009年に新シリーズとして「研修ノートシリーズ」発刊(各科16冊)※画像は2010年発行の改訂第2版循環器研修ノート
1996年
平成8年
社会・医学界のおもな出来事
- らい予防法廃止
- 丸ビル建て替えに伴い、千代田区永田町(赤坂見附駅前)に事務所移転
- 「スタンダード腹部超音波診断」(森 秀明 著)発刊※画像は「Dr.森の腹部超音波診断パーフェクト 改訂第2版」(2023年改題発行)
- 「COLOR ATLAS 産婦人科手術シリーズⅠー臨床解剖学と基本手技ー」(桑原慶紀・藤井信吾・落合和徳 編著)発刊
2012年に新シリーズとして「カラーアトラス 臨床解剖学に基づいた 新版 産婦人科手術シリーズ I 」(藤井信吾 総監修)発刊
1997年
平成9年
社会・医学界のおもな出来事
- 臓器移植法成立
1998年
平成10年
社会・医学界のおもな出来事
- ジェームズ・トムソンがヒト胚性幹細胞を発見
- 「チャイルドヘルス」創刊、以降現在まで発行中
- 「肝・胆・膵フロンティア」シリーズ(沖田 極 編)発刊、以降2001年まで刊行
1999年
平成11年
社会・医学界のおもな出来事
- 高知赤十字病院で日本初の脳死ドナーからの臓器移植実施
- 藤実彰一が三代目社長に就任
2000年~2019年
社会・医学界のおもな出来事
110年のあゆみ・各年代の代表的刊行物の紹介(雑誌/書籍)
2000年
平成12年
社会・医学界のおもな出来事
- 介護保険制度施行
- 「腎臓内科レジデントマニュアル」(今井圓裕 責任編集)発刊※画像は改訂第3版、2023年に改訂第9版発行
2001年
平成13年
社会・医学界のおもな出来事
- 乳がん治療に使用される分子標的治療薬・トラスツズマブが日本で承認される
- 「糖尿病専門医研修ガイドブック」(日本糖尿病学会 編)発刊
2002年
平成14年
- 「ADHD、LD、HFPDD、軽度MR児保健指導マニュアル」(小枝達也 編著)発刊。以降、同分野の書籍を多数刊行
2003年
平成15年
社会・医学界のおもな出来事
- ヒトゲノムの全塩基配列が解読され、遺伝学研究が大きく進展
- SARS騒動
- 高病原性鳥インフルエンザウイルス (H5N1) の大量発生
2004年
平成16年
社会・医学界のおもな出来事
- 新臨床研修制度実施
- 鳥インフルエンザ大量発生
- 「臨床研修医指導の手引き」シリーズ刊行※画像は内科(徳田安春 編)
2005年
平成17年
社会・医学界のおもな出来事
- 和共用試験(CBT・OSCE)を全国の医科大学で正式実施
- 「軽度発達障害の臨床」(横山浩之 著)発刊※画像は発達障害の臨床ーレッテル貼りで終わらせない よき成長のための診療・子育てからはじめる支援ー(2020年改題発行)
2006年
平成18年
社会・医学界のおもな出来事
- ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンが開発され、子宮頸がんの予防が可能に
- 「症例写真でよくわかる 外来でみる子どもの皮膚疾患」(馬場直子 著)発刊※画像は改訂第2版(2021年発行)
2007年
平成19年
- 「PT・OT・ST・ナースを目指す人のためのリハビリテーション総論」(椿原彰夫 責任編集)発刊
- 「内分泌代謝専門医ガイドブック」(成瀬光栄・平田結喜緒・島津章 編)発刊
- 「わかりやすい原発性アルドステロン症診療マニュアル(診断と治療社内分泌シリーズ)」(成瀬光栄,・平田結喜緒 編著)発刊
2008年
平成20年
- 「小児の皮膚トラブルFAQ」(末廣 豊・宮地良樹 編)発刊
- 「必携 脳卒中ハンドブック」(田中耕太郎・高嶋修太郎 編)発刊
2009年
平成21年
社会・医学界のおもな出来事
- 臓器移植法改正
- 臨床研修医制度見直し
- 乳がん治療に使用される分子標的治療薬・ラパチニブが日本で承認される
- 「症例から学ぶ先天代謝異常症」(日本先天代謝異常学会 編)発刊。その他、同分野の書籍を多数刊行
- 「シェーグレン症候群の診断と治療マニュアル」(日本シェーグレン症候群学会 編集)発刊※画像は改訂第3版(2018年発行)
- 「小児内分泌学」(日本小児内分泌学会 編)発刊。その他、小児科関連領域のテキストを多数刊行
2011年
平成23年
社会・医学界のおもな出来事
- 東日本大震災発生
- 「はじめて学ぶ小児内分泌(はじめて学ぶシリーズ)」(長谷川行洋 著) 発刊※画像は改訂第2版
2012年
平成24年
社会・医学界のおもな出来事
- 山中伸弥がiPS細胞の研究でノーベル生理学・医学賞を受賞
- ジェニファー・ダウドナとエマニュエル・シャルパンティエがCRISPR-Cas9を発見
2014年
平成26年
社会・医学界のおもな出来事
- 日本専門医機構発足
- 免疫チェックポイント阻害薬(ICI)のニボルマブが悪性黒色腫に対して日本で承認される
- 薬機法施行
- エボラ出血熱の治療薬が開発
- 診断と治療社 創業100年
- この頃より、電子版の刊行を本格的にはじめる
- 「小児の咳嗽診療ガイドライン」(日本小児呼吸器学会 編)発刊。その他、各種学会・研究班のガイドライン制作を手がけるようになる
- 「見て読んでわかるNASH/NAFLD診療ーかかりつけ医と内科医のために」(中島 純 監修)発刊
2015年
平成27年
社会・医学界のおもな出来事
- 大村智が線虫の寄生によって引き起こされる感染症に対する新たな治療法に関する発見でノーベル生理学・医学賞を受賞
- 「熱性けいれん診療ガイドライン2015」(日本小児神経学会 編)発刊。以降、2024年までに同学会ガイドライン5冊発刊
2016年
平成28年
社会・医学界のおもな出来事
- 大隅良典がオートファジー(自食作用)というメカニズムの解明でノーベル生理学・医学賞を受賞
2017年
平成29年
- 「ANCA関連血管炎診療ガイドライン2017」(針谷正祥・成田一衛・須田隆文 編集)発刊※画像は「ANCA関連血管炎診療ガイドライン2023」(2023年発行)
2018年
平成30年
社会・医学界のおもな出来事
- 新制度での専門医養成スタート
- 臨床研究法施行
- 本庶 佑が免疫チェックポイント阻害因子の発見とがん治療への応用でノーベル生理学・医学賞を受賞
- カリキュラム改訂に伴い「授業で現場で役に立つ!子どもの保健テキスト」、「授業で現場で役に立つ!子どもの健康と安全演習ノート」(ともに小林美由紀 編著)発刊
2020年~
社会・医学界のおもな出来事
110年のあゆみ・各年代の代表的刊行物の紹介(雑誌/書籍)
2020年
令和2年
社会・医学界のおもな出来事
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大
- 「ベーチェット病診療ガイドライン2020」(日本ベーチェット病学会 監修)発刊
- 「基礎から学ぶ女性医学」(水沼英樹 著)発刊
2021年
令和3年
社会・医学界のおもな出来事
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチン接種が日本で本格的に開始される
- 「臨床遺伝専門医テキスト」(臨床遺伝専門医制度委員会 監修)発刊。以降、2021年「IV臨床遺伝学腫瘍領域」までシリーズ5冊発刊※画像は①臨床遺伝学総論
- 「脳波判読オープンキャンパス 誰でも学べる7STEP」(音成秀一郎・池田昭夫 著)発刊
- 「関節リウマチ診療ガイドライン2020」(日本リウマチ学会 編集)発刊※画像は「日本リウマチ学会 関節リウマチ診療ガイドライン2024改訂-若年性特発性関節炎 少関節炎型・多関節型診療ガイドラインを含む」(2024年改題発行)
2022年
令和4年
社会・医学界のおもな出来事
- ヒトゲノム完全解読
- 「めざせ即戦力レジデント!小児科ですぐに戦えるホコとタテ 小児科ではコモンなディジーズの診かた」(岡本光宏 著)発刊
2023年
令和5年
- 藤実正太が四代目社長に就任
- 「内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医研修ガイドブック」(日本内分泌学会・日本糖尿病学会 編)発刊
2024年
令和6年
- 診断と治療社 創業110年
※本ページで紹介した書籍や雑誌は各年代での代表的な刊行物の一例です。
ページの都合上、紹介することが叶わなかった多数の書籍や雑誌があります。